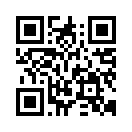本沢温泉は、登山客以外も訪れる秘湯の宿。
といっても、歩いてくる以外方法はありませんが(冬は雪上車でのお迎えがあるらしい)。
本沢温泉といえば有名なのは日本一高いところにある野天風呂=「雲上の湯」ですね。
但し、「雲上の湯」は登山道を5分ほど上らないといけません。浴槽以外、更衣室などの施設もありません。
悪いことに、私がいったこの日は、直前の台風で土砂が流れ込み、「雲上の湯」は壊れていました。前の投稿で夏沢峠の「やまびこ荘」のご主人が本沢温泉の手伝いに狩り出されていると書きましたが、それはこの「雲上の湯」の補修工事の為でした。
私が訪れたとき、土砂は既に取り除かれていましたが、どうやらどこかからお湯が漏れるようで、お湯が溜まらず、結局足湯だけしか楽しめませんでした。


残念ですが仕方ありませんね。また、捲土重来を期します。
本沢温泉には内湯もあります。
「こけももの湯」といって、「雲上の湯」とは源泉・泉質が異なり、男女別になっています。
「雲上の湯」はぬるいお湯ですが、「こけももの湯」は超熱いお湯です。
しかも、ヌルめるための水道もありません。
完全なる無加水かけ流しです。
なので、せめてフタになっている重い木の板で、湯もみしてから入るのが吉です。
それでも、熱いのが苦手な人はつかれないでしょう。
私も日焼けのキツイ両腕の外側は、お湯につけられませんでした。
でも、温泉らしい良いお湯(私の好み)で、とっても暖まりましたよ。
「こけももの湯」のもう一つの問題は、(屋内ですが)かなり階段を下りていかないといけないことです。これが疲れた足にはこたえます(笑)。
あと、「雲上の湯」はもちろん、「こけももの湯」もシャンプー、石鹸は使用できません。
本沢温泉でも、私の住環境は良好でした。
相部屋で申し込みましたが、通常20名で利用するらしい大広間を
私を含めて2名だけで使えるという状況でした。
他にも、10名くらいのグループやご夫婦等の宿泊客がおられましたが、みなさん個室利用?
いずれにせよ、かなり空いていた方だと思います。
飲料水は、外に誰でも自由に飲めるようにしてくれている外、屋内の洗面所の水も飲料可です。
トイレもすごく清潔です。但し、トイレットペーパーは便器に流さず、横にあるフタつきのゴミ箱に別途捨てる必要があります。
本沢温泉のお食事も美味しかったですが、疲れてたので撮るのを忘れました。
あと、生ジョッキを1杯、さらに、大部屋で同宿したUさんと一緒に、にごり酒のピッチャー(大)を頼んで飲みましたので、食後は直ぐに寝付いて、朝まで熟睡でした。
さて、最終日。稲子湯へ降りてJR小海駅行きのバスに乗ります。11時45分稲子湯発のバスに間に合うよう、8時15分に本沢温泉を出発。
ここからの帰りは、同宿したUさんとご一緒させていただきました。
Uさんはやまびこ荘の常連客。この日は、やまびこ荘のご主人が雲上の湯の修理のため山小屋を閉めざるを得なかった為、本沢温泉に宿泊されたのでした。
そんな方ですので、歩くスピードは違うだろうし、私はきっと遅れるだろうから、その時は置いていってくださいねと一言いっておきました。
本沢温泉から10分ほど幅の広い林道を下ったところから、みどり池方面への山道が左手にはじまります。この道に入ります。

10-15分ほどちょっとした登りが続きますが、その後は平坦に近い道になります。
途中、中山峠への道を分岐し、9時15分(本沢温泉から1時間ほど)
みどり池に到着。

ここ、写真のとおり、すごく綺麗です!
透明度の高い水が波もたてずに横たわり、その向こうに鮮やかな緑、背景には切り立った岩山(東天狗岳?ニュウ?)、おもわず息をのむ風景です。
池のほとりには「しらびそ小屋」が立っています。

中には入ってないのでよくわかりませんが、
女性に人気らしく、ここからのくだりにも女性だけのパーティーに結構あいました。
少なくとも、ロケーションは抜群ですね。
みどり池の前後の山道も、とっても気持ちいいです。
平坦で、木陰で涼しいし、木道があるところもあったります。
冬にスノーシューなんか履いて歩くのかな?
みどり池からは本格的に下りになります。稲子湯まで標高差は500メートル。
道幅は広いものの、岩がゴロゴロしてたりします。
以前は途中、良さ気な山道だったそうですが、平成23年の台風でルートが変わり、単調な道になったそうです。ただ、知らずに旧道(屏風橋ルート)を登ってきている人も結構います。大丈夫なのか?
やがで車道を数回横切り、4度目に車道に出ると、橋と、その向こうにゲートが見えてきました。

ゲートの向こうには車がいっぱい止まっていて、人も結構います。
バス停もありました。ここが「みどり池入口」なんですね。

車やバスで来る場合、ここが一番歩く距離を短くできそうです。
但し、ここまでくるバスはそんなに多くなく、この時間もありませんでしたので、引き続き稲子湯をめざします。
再び山道に入り(車道を1度横切る)、10時30分、稲子湯に到着。

コースタイム2時間50分のところを、休憩コミで2時間15分できちゃいました。
Uさん早すぎ!
まあ、そのおかげで稲子湯に立ち寄ることができましたけどね。
日帰り入浴は600円です。
ここ、よく分からないんですが、熱いお湯と冷たいお水が出ていて、
湯船のお湯が熱かったら、赤いバルブをまわして冷たいお水を足してぬるめます。
但し、この冷たいお水というのも実は炭酸泉の鉱泉なんですね。
コップがおいてあって飲む事ができるんですが、炭酸飲料みたいに凄くシュワシュワしてます(硫黄の風味がしますが)。こういうの初めてでチョット面白かったです。
*後日ネットで調べてみると、熱いお湯は鉱泉が加熱されているみたいですね。
湯上りには、滝沢牧場というところのアイスクリーム(400円)を満喫。
何種類かありましたが、私はあまり見かけない花豆アイスを選択。
小豆より上品な味で、美味しくいただきました。
稲子湯は映画「岳」のロケ地なんですね。
小栗旬さん、長沢まさみさんをはじめ、出演者やスタッフのサインがありました。

予定通り、11時45分にバスが稲子湯を発車。
小海駅からJR小海線に乗り、佐久平駅で長野新幹線に乗り換え帰京。
*小海駅で駅員が一人しかおらず、その人が長電話するものだから、
(新幹線の)切符がなかなか買えずにハラハラしましたけどね。
今回は本当に充実した南八ヶ岳縦走でした。
全ての自然と人に感謝!
12時25分、重い腰を上げて根石岳頂上を出発、今回最後の山、天狗岳に向います。
根石岳から白砂の道を緩やかに下っていくと、やがて本沢温泉へ降りる白砂新道入口の標識があります。
ここを通り過ぎたあたりからザレた登りがはじまり、それがやがて岩の稜線になります。
一つピークを超え、さらに小さな鉄製の網上のブリッジを超えると、もう東天狗岳の頂上です。
12時55分着。標高2640メートル。


(この写真の標識には標高2646mと書かれていますが、これは西天狗岳の標高じゃないかと思います。東西両天狗岳の高い方を採用して書いた?昭文社の地図や、Wilipedia等のウェブサイト上では東天狗岳は2640メートルとなっています)
北の方には、一部が白く縞枯れた北八ヶ岳の樹林が広がっています。
黒百合ヒュッテも見えてますね。

西には、もう一つの天狗岳、西天狗岳が目の前に存在感をみせてます。

西天狗まではコースタームで往復40分。
この時点で時間的にはまだ早いし、スケジュールでも西天狗に寄ることにしていました。
ただ、見るからに、一旦かなり降りてから登り返さないといけません。
へろへろオジサンに残る体力はわずか(笑)でしたので、
西天狗まで行くかどうしようか悩みましたよ。
でも.....
標高は西天狗の方が東天狗よりわずかですが高いんですね。
それと、先ほど会った根石岳小屋の方の話によれば、東天狗では見えない横岳が、西天狗からは見えるらしい。
そういう魅力に惹かれ、また、途中で荷物(ザック)を鞍部に置いて空荷で往復するという手抜きをすることにして、予定どおり西天狗岳に行くことにしました(東天狗に荷物を置いたままいくのはさすがに怖い)。

西天狗岳からは赤岳の威容が素晴らしい。
確かに、ちょびっとですが、硫黄岳のうしろに横岳も顔をのぞかせていますね。

西天狗から見た東天狗はこんな感じです。

鞍部でザックをピックアップして東天狗山頂に戻ると時刻は午後2時。
あとは本沢温泉に向けて降りるのみ!!
25分ほどで、先ほど通り過ぎた「白砂新道」への分岐点です。

ここから白砂新道に入って本沢温泉をめざします。
しかし、この道が大変でした!ここまでずっと歩いてきた八ヶ岳の他の道とは違って、白砂新道はあまり整備されていませんでした。
先日の台風の影響もあるのでしょうか、倒れた木が道をふさいでいたり、踏み後が弱弱しかったりで、迷うところも結構あります(特に、下り始めのあたりは、)。
時々木に結び付けられている目印のテープを見失わないように注意が必要です。
それに、眺望のないところを、ただただガンガン下っていくので、疲れた足にはこたえます(これはまあ、下りというのは全てそういうものかもしれませんが)。
結局、コースタイム50分のところを、休憩を含めて1時間半もかかりました。
時間が掛かりすぎたことや、次第に暗くなってきたこともあって、途中結構不安になりました。まあ、その度に、小さな標識があって胸をなでおろしましたが、暗い時や天候の悪いときは迷うかも。
ようやく「本沢温泉まであと10分」の標識が現れ、小さな水の流れを3本ほど渡ると、本沢温泉に到着。15時55分。
根石岳から白砂の道を緩やかに下っていくと、やがて本沢温泉へ降りる白砂新道入口の標識があります。
ここを通り過ぎたあたりからザレた登りがはじまり、それがやがて岩の稜線になります。
一つピークを超え、さらに小さな鉄製の網上のブリッジを超えると、もう東天狗岳の頂上です。
12時55分着。標高2640メートル。


(この写真の標識には標高2646mと書かれていますが、これは西天狗岳の標高じゃないかと思います。東西両天狗岳の高い方を採用して書いた?昭文社の地図や、Wilipedia等のウェブサイト上では東天狗岳は2640メートルとなっています)
北の方には、一部が白く縞枯れた北八ヶ岳の樹林が広がっています。
黒百合ヒュッテも見えてますね。

西には、もう一つの天狗岳、西天狗岳が目の前に存在感をみせてます。

西天狗まではコースタームで往復40分。
この時点で時間的にはまだ早いし、スケジュールでも西天狗に寄ることにしていました。
ただ、見るからに、一旦かなり降りてから登り返さないといけません。
へろへろオジサンに残る体力はわずか(笑)でしたので、
西天狗まで行くかどうしようか悩みましたよ。
でも.....
標高は西天狗の方が東天狗よりわずかですが高いんですね。
それと、先ほど会った根石岳小屋の方の話によれば、東天狗では見えない横岳が、西天狗からは見えるらしい。
そういう魅力に惹かれ、また、途中で荷物(ザック)を鞍部に置いて空荷で往復するという手抜きをすることにして、予定どおり西天狗岳に行くことにしました(東天狗に荷物を置いたままいくのはさすがに怖い)。

西天狗岳からは赤岳の威容が素晴らしい。
確かに、ちょびっとですが、硫黄岳のうしろに横岳も顔をのぞかせていますね。

西天狗から見た東天狗はこんな感じです。

鞍部でザックをピックアップして東天狗山頂に戻ると時刻は午後2時。
あとは本沢温泉に向けて降りるのみ!!
25分ほどで、先ほど通り過ぎた「白砂新道」への分岐点です。

ここから白砂新道に入って本沢温泉をめざします。
しかし、この道が大変でした!ここまでずっと歩いてきた八ヶ岳の他の道とは違って、白砂新道はあまり整備されていませんでした。
先日の台風の影響もあるのでしょうか、倒れた木が道をふさいでいたり、踏み後が弱弱しかったりで、迷うところも結構あります(特に、下り始めのあたりは、)。
時々木に結び付けられている目印のテープを見失わないように注意が必要です。
それに、眺望のないところを、ただただガンガン下っていくので、疲れた足にはこたえます(これはまあ、下りというのは全てそういうものかもしれませんが)。
結局、コースタイム50分のところを、休憩を含めて1時間半もかかりました。
時間が掛かりすぎたことや、次第に暗くなってきたこともあって、途中結構不安になりました。まあ、その度に、小さな標識があって胸をなでおろしましたが、暗い時や天候の悪いときは迷うかも。
ようやく「本沢温泉まであと10分」の標識が現れ、小さな水の流れを3本ほど渡ると、本沢温泉に到着。15時55分。
9時40分、硫黄岳から縦走路を夏沢峠へと向います。
<硫黄岳から夏沢峠へ向う道。向こうにはこれから向う天狗岳や根石岳が見えています。>

東側(上の写真の右手)に爆裂火口があるので、天候が悪い日はケルンを頼りに落ちないよう注意しましょう。
この日は快晴でしたので、ひたすら降りるだけ。
やがて道はザレが強くなり、傾斜もきつくなっていきます。さらにひたすら降り続けます。
10時25分、夏沢峠に到着。標高2440メートル。

夏沢峠には「やまびこ荘」「ヒュッテ夏沢」の2つの山小屋があります。
上の写真右側がやまねが住みついている事で有名な「やまびこ荘」、左側が「ヒュッテ夏沢」です。
この日は「ヒュッテ夏沢」は営業してませんでした。また、後で得た情報によると、午後からは「やまびこ荘」が本沢温泉へある仕事の応援に行ったため、「やまびこ荘」もしまったみたいです(やまびこ荘と本沢温泉は同じ資本系列)。
小屋の天狗岳側に座れるところがあったので、そこでしばし休憩後、
夏沢峠って、日本3大峠なんですよね。3大峠というのは、北アルプスの針ノ木峠、奥秩父の雁坂峠、そしてここ、夏沢峠だそうです(一説には夏沢峠の代わりに南アルプスの三伏峠が数えられることもあるようですが)。昔は八ヶ岳をこえる為の交通の要衝だったのかもしれませんね。
でも、そんなことを感じさせない、とても静かで素朴な峠でした。
10時35分、天狗岳方面へ登り返します。

ここから根石岳山荘までの道は、樹林帯の中を緩やかに上る道で、とても気持ち良いです。初心者にはお勧めですね。
「南八ヶ岳」という場合、一般に夏沢峠までを指し、ここから北は「北八ヶ岳」に分類されます。よく、岩登りを楽しめるアルペン風情の「南八ヶ岳」と、樹林や湖沼が美しい「北八ヶ岳」と対比されますが、この道を歩くと、「ここは南八ヶ岳ではなく北八ヶ岳なんだな」と感じずにはおれません。
やがて「箕冠山」とかかれた分岐点に到着しました。
左に折れるとオーレン小屋への道、根石岳へ向う縦走路は右に折れます。
この分岐点も林の中にあって眺望は効きません。

箕冠山の分岐からチョットだけ下ると、直ぐに樹林帯を抜け出し視界が開け、
根石岳が目の前にいきなり現れます。

左手を見ると、根石岳山荘が建っています。

何ヶ月か前にテレビで元チェッカーズの藤井フミヤさんがこの小屋に立ち寄ってたのを見たので、私も何か食べようかなと思ったんですが、誰もいなかったのであきらめました。
ただ、この小屋はまん前に水が湧き出しているんですね(周囲の山との高度さがあまりないのに不思議です)。そこでお水を補充しました。
その後、根石岳に上る途中で、山荘の従業員の方が登山道の整備をされているのに会いました。
赤岳のTシャツを着ておられたんですが、「根石岳山荘の方ですか?」というと、「そうです」ということでした(笑)。Tシャツはお休みに赤岳に遊びにいった時に買ったらしい。あっ、小屋でお水をもらった話もしましたが、お金もいらないって言われました。
根石岳の頂上に登って、昼飯がわりにビスケットを食べていると、この従業員の方も上がってこられて、道標の建て直しをされていました。
何でも、先日の台風で倒れたとのこと。
これ一人でやるの大変じゃない?ということで、私も非力ながらチョットだけお手伝い。(といっても、ハンマーで打ち込むときに標識を持ってるとか、小さな岩を運ぶ程度だけど)
<作業前の道標>

<作業後の道標>

こんな風に、山小屋の方々の努力によって、我々は快適で安全な山歩きが出来るんですね。改めて感謝です。
根石岳から南を振り返れば、さきほど下りてきた硫黄岳、そして赤岳や阿弥陀岳も見えますね。

北には、これからいく最後の目的地、天狗岳が目の前です。
(続く)
<硫黄岳から夏沢峠へ向う道。向こうにはこれから向う天狗岳や根石岳が見えています。>

東側(上の写真の右手)に爆裂火口があるので、天候が悪い日はケルンを頼りに落ちないよう注意しましょう。
この日は快晴でしたので、ひたすら降りるだけ。
やがて道はザレが強くなり、傾斜もきつくなっていきます。さらにひたすら降り続けます。
10時25分、夏沢峠に到着。標高2440メートル。

夏沢峠には「やまびこ荘」「ヒュッテ夏沢」の2つの山小屋があります。
上の写真右側がやまねが住みついている事で有名な「やまびこ荘」、左側が「ヒュッテ夏沢」です。
この日は「ヒュッテ夏沢」は営業してませんでした。また、後で得た情報によると、午後からは「やまびこ荘」が本沢温泉へある仕事の応援に行ったため、「やまびこ荘」もしまったみたいです(やまびこ荘と本沢温泉は同じ資本系列)。
小屋の天狗岳側に座れるところがあったので、そこでしばし休憩後、
夏沢峠って、日本3大峠なんですよね。3大峠というのは、北アルプスの針ノ木峠、奥秩父の雁坂峠、そしてここ、夏沢峠だそうです(一説には夏沢峠の代わりに南アルプスの三伏峠が数えられることもあるようですが)。昔は八ヶ岳をこえる為の交通の要衝だったのかもしれませんね。
でも、そんなことを感じさせない、とても静かで素朴な峠でした。
10時35分、天狗岳方面へ登り返します。

ここから根石岳山荘までの道は、樹林帯の中を緩やかに上る道で、とても気持ち良いです。初心者にはお勧めですね。
「南八ヶ岳」という場合、一般に夏沢峠までを指し、ここから北は「北八ヶ岳」に分類されます。よく、岩登りを楽しめるアルペン風情の「南八ヶ岳」と、樹林や湖沼が美しい「北八ヶ岳」と対比されますが、この道を歩くと、「ここは南八ヶ岳ではなく北八ヶ岳なんだな」と感じずにはおれません。
やがて「箕冠山」とかかれた分岐点に到着しました。
左に折れるとオーレン小屋への道、根石岳へ向う縦走路は右に折れます。
この分岐点も林の中にあって眺望は効きません。

箕冠山の分岐からチョットだけ下ると、直ぐに樹林帯を抜け出し視界が開け、
根石岳が目の前にいきなり現れます。

左手を見ると、根石岳山荘が建っています。

何ヶ月か前にテレビで元チェッカーズの藤井フミヤさんがこの小屋に立ち寄ってたのを見たので、私も何か食べようかなと思ったんですが、誰もいなかったのであきらめました。
ただ、この小屋はまん前に水が湧き出しているんですね(周囲の山との高度さがあまりないのに不思議です)。そこでお水を補充しました。
その後、根石岳に上る途中で、山荘の従業員の方が登山道の整備をされているのに会いました。
赤岳のTシャツを着ておられたんですが、「根石岳山荘の方ですか?」というと、「そうです」ということでした(笑)。Tシャツはお休みに赤岳に遊びにいった時に買ったらしい。あっ、小屋でお水をもらった話もしましたが、お金もいらないって言われました。
根石岳の頂上に登って、昼飯がわりにビスケットを食べていると、この従業員の方も上がってこられて、道標の建て直しをされていました。
何でも、先日の台風で倒れたとのこと。
これ一人でやるの大変じゃない?ということで、私も非力ながらチョットだけお手伝い。(といっても、ハンマーで打ち込むときに標識を持ってるとか、小さな岩を運ぶ程度だけど)
<作業前の道標>

<作業後の道標>

こんな風に、山小屋の方々の努力によって、我々は快適で安全な山歩きが出来るんですね。改めて感謝です。
根石岳から南を振り返れば、さきほど下りてきた硫黄岳、そして赤岳や阿弥陀岳も見えますね。

北には、これからいく最後の目的地、天狗岳が目の前です。
(続く)
さて、次の目的地は硫黄岳です。
8時ごろ横岳を出立。
横岳山頂から硫黄岳側へ下りる道には、最初にいくつかクサリ場があります。


でも、10-15分で通過できるでしょう。
そんなに高度感も感じませんでした。
あとはのんびりした絶景のプロムナードです。
横岳を振り返るとこんな感じです。

最後に、ザレた坂をジグザグ下れば、硫黄岳小屋に到着。8時30頃。
硫黄岳小屋の入口は、縦走路から見て小屋の反対側(谷側)にありますので、
ほんのちょっとだけ下りていきます(その分、谷側の景色が開ける)。

念の為、ここでも水を手に入れておこうと、「いろはす」1本400円を購入した後で、
飲料水が1リットル100円で販売されていることに気がつきました。
地図では水場の表示はなかったですが、沢から組み上げているのかもしれませんね。
いろはすは予備としてしまっておいて、水筒に水を満たしました。
ここにも皇太子がお見えになっているんですね。
写真の玄関左脇にあるのは、皇太子のご宿泊記念碑です。
まだ浩之宮様と名乗っておられた頃、昭和61年8月末だそうです。
皇太子は結構いろんなところに登られておられるので、
もう最近は驚かなくなりましたけどね。
硫黄岳はもう硫黄岳小屋の目の前にデンと横たわっています。

写真中央左寄りの崖をよけて右側を登り、崖の上部を横切っていく道が見えていますね。
よく見ると、崖を囲むように何かがたくさん立っています。
これは下のようなケルン(石積みの塔)です。

このあたりはよく霧が出るらしく、
このケルンは霧の時に、登山者が崖に落ちないようにという配慮で
立てられているのでしょう。
上の写真の崖、最初は有名な「爆裂火口」かなと思ってたんですが、違いました。
「爆裂火口」はもっと凄くて、反対側にありました。

硫黄岳って、遠くから見ると、ゆったり大きく見えますが、
実は爆発で吹っ飛んだり、両側に崖があったりで、やせ細ってるのかもしれませんね。
9時20分、硫黄岳山頂に到着。標高2760メートル。
この山の頂上は、とてもだだっ広いです。


小さめの石ばかりなので座るとお尻が痛く、
かといって、草や大きな岩もないので、ちょっと休憩しづらいと感じました。
ただ、硫黄岳山頂も眺望は素晴らしいです。
南は横岳、赤岳、権現岳、阿弥陀岳、北に天狗岳や蓼科山等の八ヶ岳の山々が連なり、
中央アルプス、御嶽山、北アルプスなどが一望です。
<硫黄岳から南を望む>

<硫黄岳から西を望む>

上の写真の緑のピークは「峰の松目」というところですね。
眺望が聞かないので人気がないですが、説によっては八ヶ岳の8つの峰の
一つに数えられています(例えば、有名な深田久弥氏の「日本百名山」)。
峰の松目の右下方にオーレン小屋が見えますね。
あそこまで硫黄岳山頂から1時間で下りられます。
(続く)
8時ごろ横岳を出立。
横岳山頂から硫黄岳側へ下りる道には、最初にいくつかクサリ場があります。


でも、10-15分で通過できるでしょう。
そんなに高度感も感じませんでした。
あとはのんびりした絶景のプロムナードです。
横岳を振り返るとこんな感じです。

最後に、ザレた坂をジグザグ下れば、硫黄岳小屋に到着。8時30頃。
硫黄岳小屋の入口は、縦走路から見て小屋の反対側(谷側)にありますので、
ほんのちょっとだけ下りていきます(その分、谷側の景色が開ける)。

念の為、ここでも水を手に入れておこうと、「いろはす」1本400円を購入した後で、
飲料水が1リットル100円で販売されていることに気がつきました。
地図では水場の表示はなかったですが、沢から組み上げているのかもしれませんね。
いろはすは予備としてしまっておいて、水筒に水を満たしました。
ここにも皇太子がお見えになっているんですね。
写真の玄関左脇にあるのは、皇太子のご宿泊記念碑です。
まだ浩之宮様と名乗っておられた頃、昭和61年8月末だそうです。
皇太子は結構いろんなところに登られておられるので、
もう最近は驚かなくなりましたけどね。
硫黄岳はもう硫黄岳小屋の目の前にデンと横たわっています。

写真中央左寄りの崖をよけて右側を登り、崖の上部を横切っていく道が見えていますね。
よく見ると、崖を囲むように何かがたくさん立っています。
これは下のようなケルン(石積みの塔)です。

このあたりはよく霧が出るらしく、
このケルンは霧の時に、登山者が崖に落ちないようにという配慮で
立てられているのでしょう。
上の写真の崖、最初は有名な「爆裂火口」かなと思ってたんですが、違いました。
「爆裂火口」はもっと凄くて、反対側にありました。

硫黄岳って、遠くから見ると、ゆったり大きく見えますが、
実は爆発で吹っ飛んだり、両側に崖があったりで、やせ細ってるのかもしれませんね。
9時20分、硫黄岳山頂に到着。標高2760メートル。
この山の頂上は、とてもだだっ広いです。


小さめの石ばかりなので座るとお尻が痛く、
かといって、草や大きな岩もないので、ちょっと休憩しづらいと感じました。
ただ、硫黄岳山頂も眺望は素晴らしいです。
南は横岳、赤岳、権現岳、阿弥陀岳、北に天狗岳や蓼科山等の八ヶ岳の山々が連なり、
中央アルプス、御嶽山、北アルプスなどが一望です。
<硫黄岳から南を望む>

<硫黄岳から西を望む>

上の写真の緑のピークは「峰の松目」というところですね。
眺望が聞かないので人気がないですが、説によっては八ヶ岳の8つの峰の
一つに数えられています(例えば、有名な深田久弥氏の「日本百名山」)。
峰の松目の右下方にオーレン小屋が見えますね。
あそこまで硫黄岳山頂から1時間で下りられます。
(続く)
2013年9月20日。
この日は赤岳天望荘を出発して横岳・硫黄岳・天狗岳とめぐり、本沢温泉へと下りる行程です。
6時30分、赤岳天望荘を出発。
5分も行けば、小さなお地蔵さんのある「地蔵の頭」です。
地蔵尾根からの登り道が合流します。

お地蔵さんが向いている先はというと....

岩がゴツゴツしてて、これまたシンドそうですね。
でも、この道が赤岳に登るルートとしては一番難易度がマシで最短らしいですので、
今度はここから登ってみようかな。
赤岳から横岳へ向う道は尾根伝いですので、そんなにメチャクチャな登りはありませんが、ハシゴやクサリ場は結構あります。大人なら問題ないと思います(子供は大変かもしれないけど)。

それに、そこらじゅう絶景だらけなので、気持ちも良いですしね。
ちょっと、天望荘と赤岳を振り返ってみました。
このあたりからの赤岳はカッコいいですね。

7時20分、「大権現」と彫られた石碑が立つピークにきました。
石尊峰ってヤツかな?で、向こうに見えるのが横岳主峰の「奥の院」でしょうね。

案の定、5分ほどで杣添尾根への道の分岐点をとおった後、
7時40分頃、横岳山頂に到着です。1829メートル。

「奥の院」という別名があるのに、お社とか祠とかないのがちょっと不思議。
横岳の山頂も、もちろん素晴らしいパノラマです。
南には赤岳と天望荘、中岳、阿弥陀岳、その向こうにチョット顔を出している権現岳、バックには南アルプス。

北にはコレから行く硫黄岳、その後ろに顔をのぞかせる(西)天狗岳、北八ヶ岳の山々。

これまで同様、北アルプス、御岳、中央アルプス、富士山などもキレイに見えます。
<横岳から北アルプスを望む>

西側の崖を見下ろすと、大きな岩が突き出しています。

これが「小同心」かな?
写真を見ると、先端まで道もついてますね。一般人向けじゃないと思いますが。
小さく見えている山小屋は、赤岳鉱泉です。
(続く)
この日は赤岳天望荘を出発して横岳・硫黄岳・天狗岳とめぐり、本沢温泉へと下りる行程です。
6時30分、赤岳天望荘を出発。
5分も行けば、小さなお地蔵さんのある「地蔵の頭」です。
地蔵尾根からの登り道が合流します。

お地蔵さんが向いている先はというと....

岩がゴツゴツしてて、これまたシンドそうですね。
でも、この道が赤岳に登るルートとしては一番難易度がマシで最短らしいですので、
今度はここから登ってみようかな。
赤岳から横岳へ向う道は尾根伝いですので、そんなにメチャクチャな登りはありませんが、ハシゴやクサリ場は結構あります。大人なら問題ないと思います(子供は大変かもしれないけど)。

それに、そこらじゅう絶景だらけなので、気持ちも良いですしね。
ちょっと、天望荘と赤岳を振り返ってみました。
このあたりからの赤岳はカッコいいですね。

7時20分、「大権現」と彫られた石碑が立つピークにきました。
石尊峰ってヤツかな?で、向こうに見えるのが横岳主峰の「奥の院」でしょうね。

案の定、5分ほどで杣添尾根への道の分岐点をとおった後、
7時40分頃、横岳山頂に到着です。1829メートル。

「奥の院」という別名があるのに、お社とか祠とかないのがちょっと不思議。
横岳の山頂も、もちろん素晴らしいパノラマです。
南には赤岳と天望荘、中岳、阿弥陀岳、その向こうにチョット顔を出している権現岳、バックには南アルプス。

北にはコレから行く硫黄岳、その後ろに顔をのぞかせる(西)天狗岳、北八ヶ岳の山々。

これまで同様、北アルプス、御岳、中央アルプス、富士山などもキレイに見えます。
<横岳から北アルプスを望む>

西側の崖を見下ろすと、大きな岩が突き出しています。

これが「小同心」かな?
写真を見ると、先端まで道もついてますね。一般人向けじゃないと思いますが。
小さく見えている山小屋は、赤岳鉱泉です。
(続く)